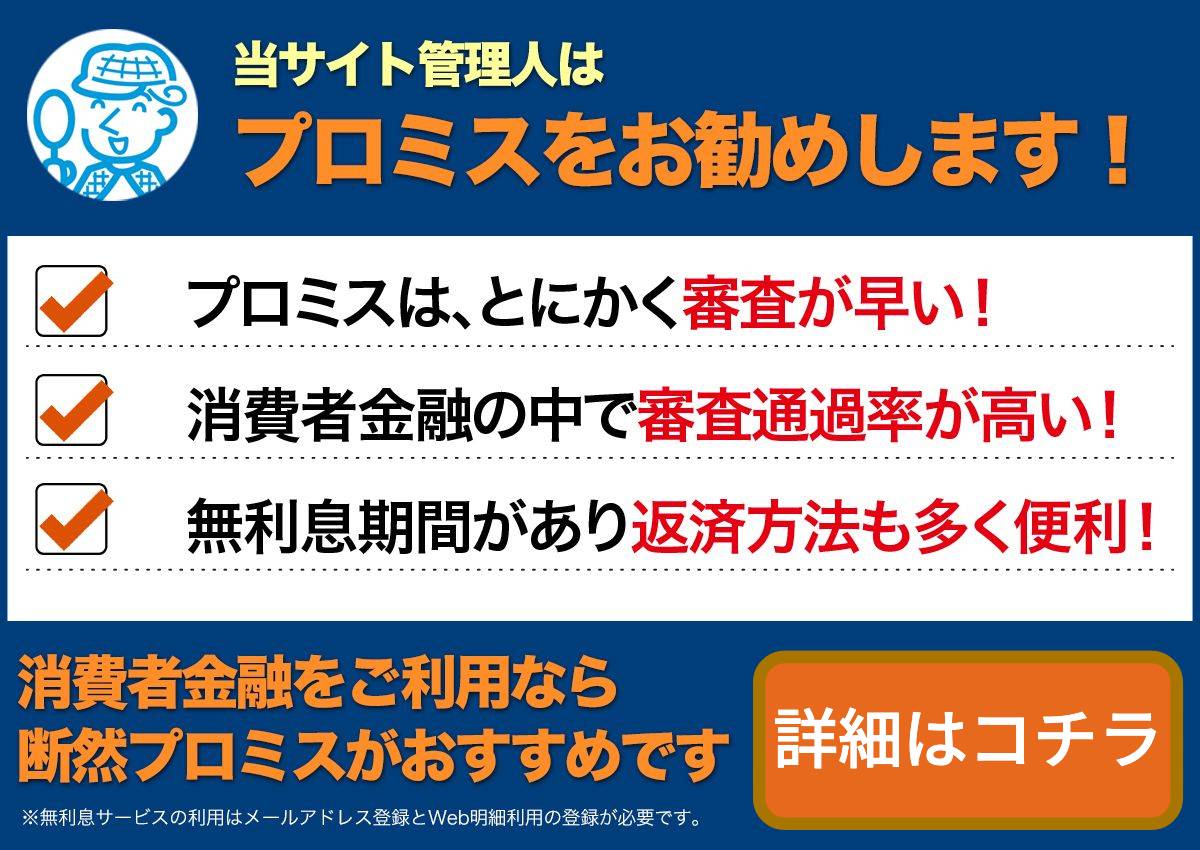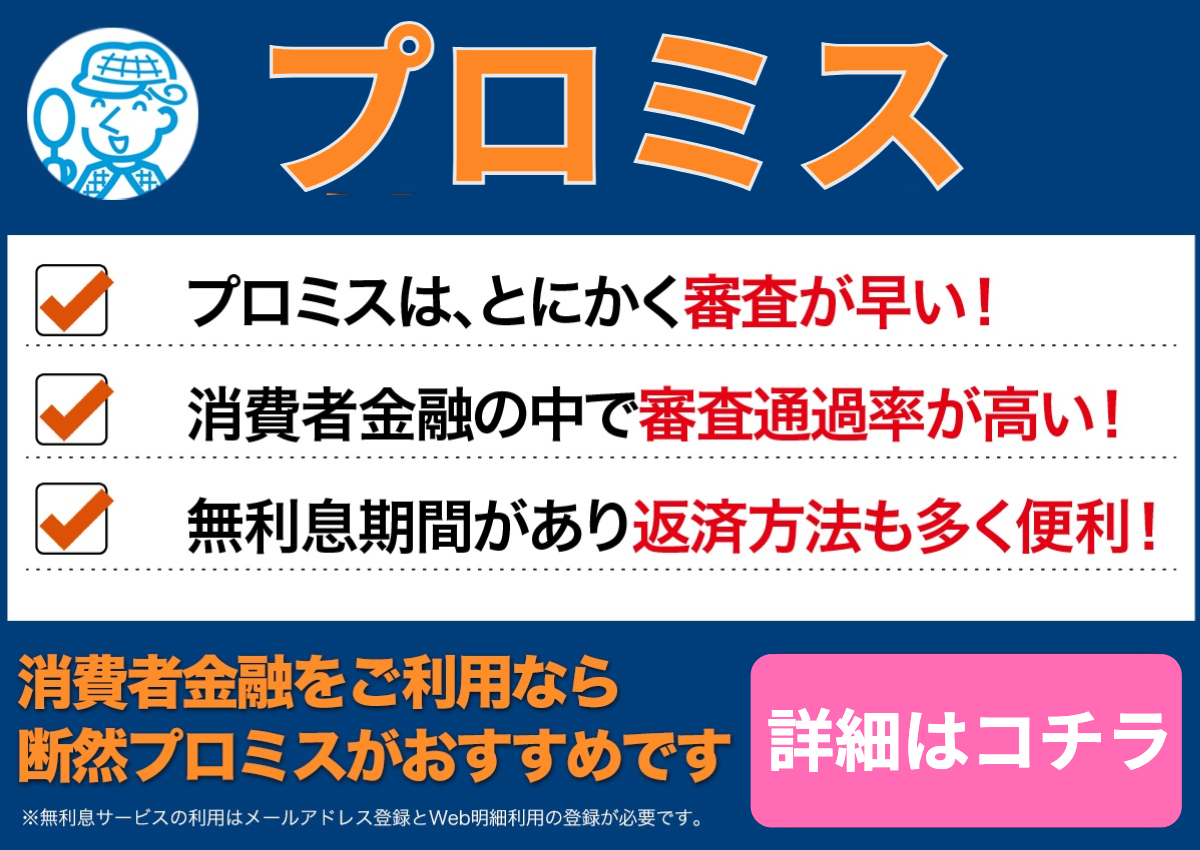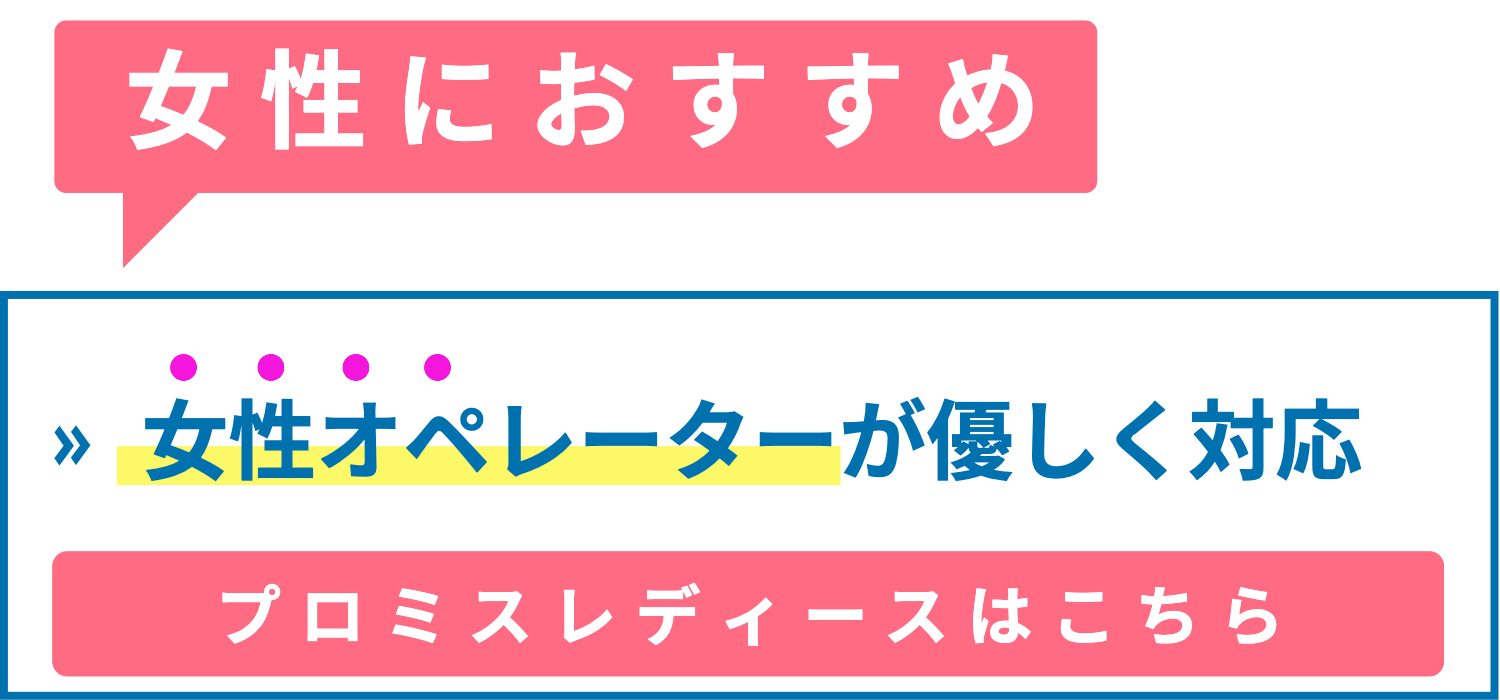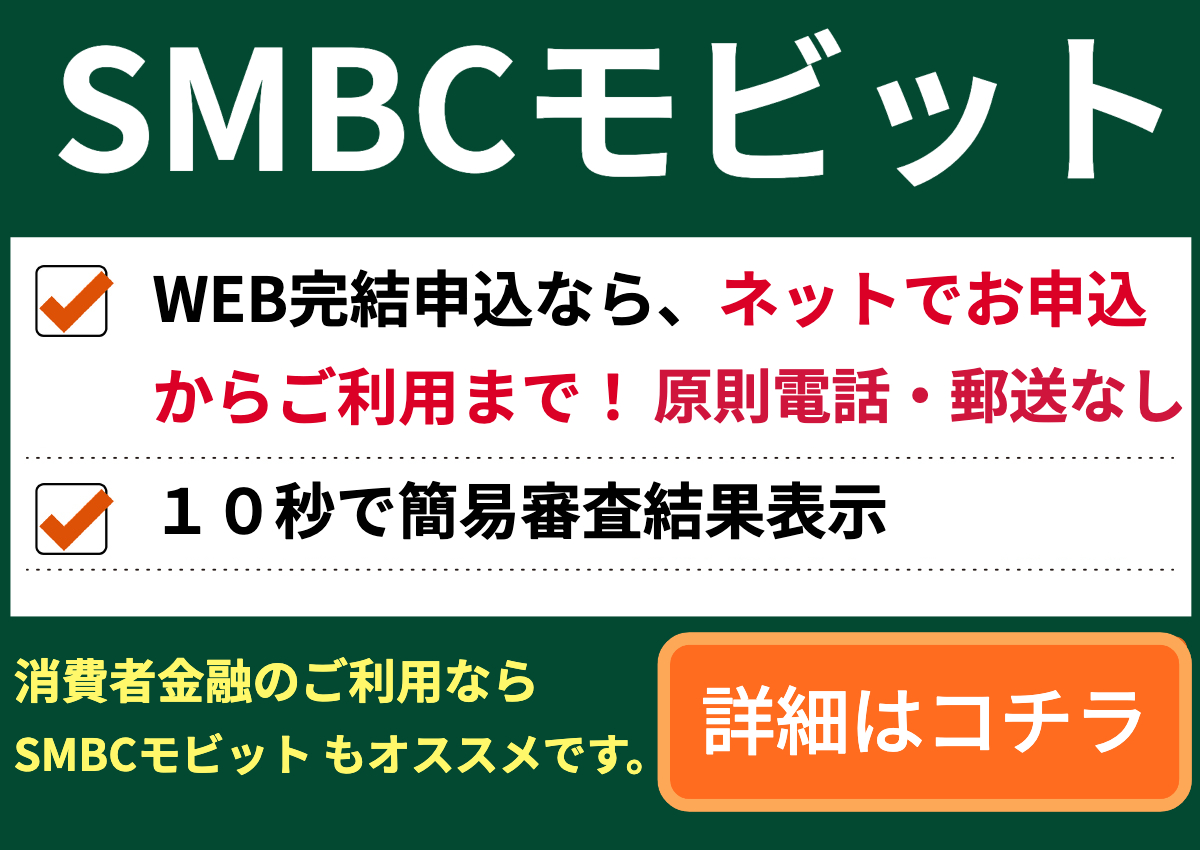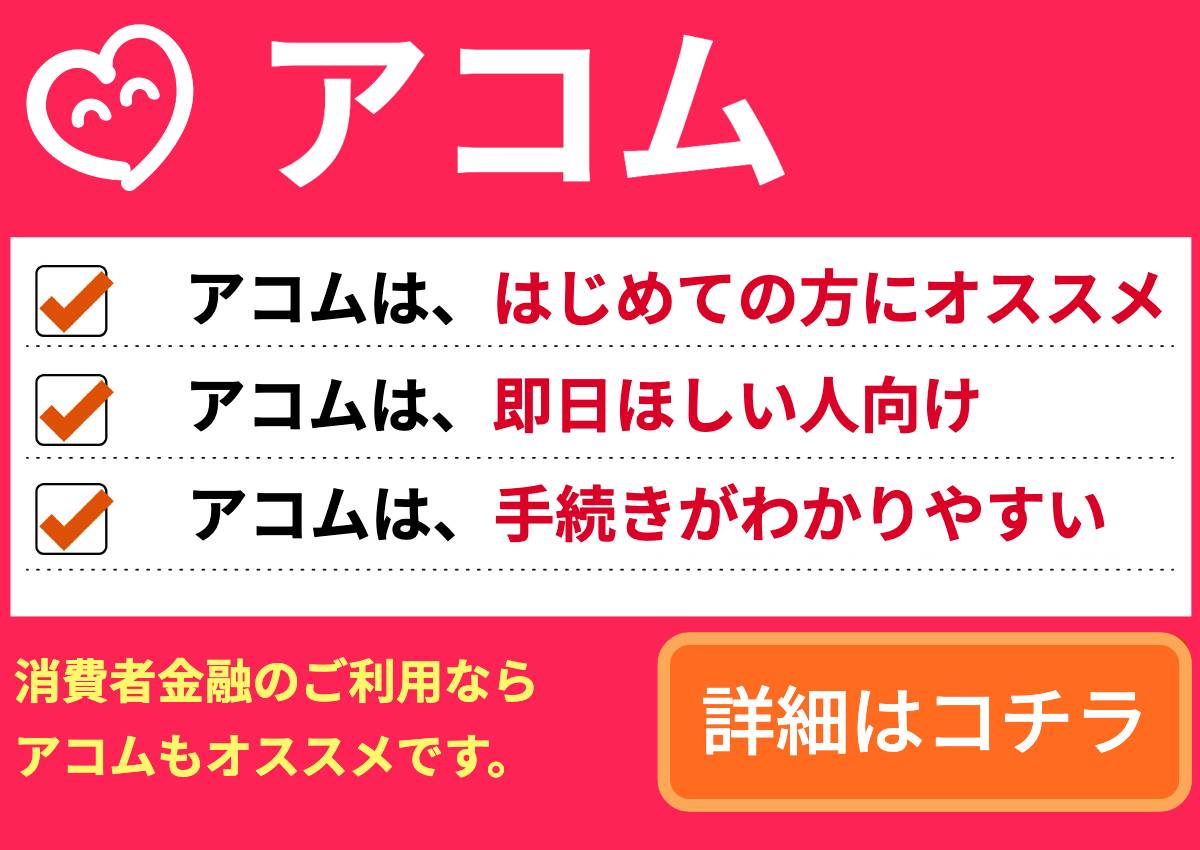※当サイトはプロモーションが含まれています

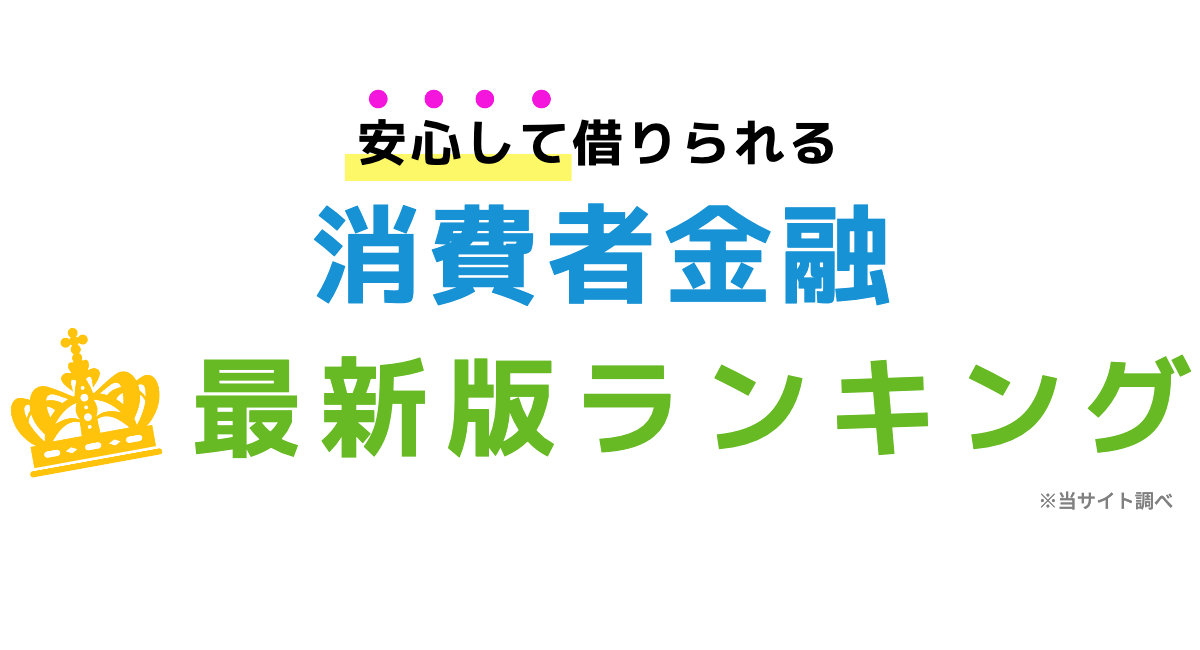
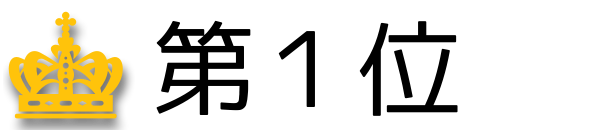
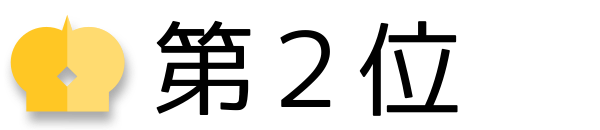
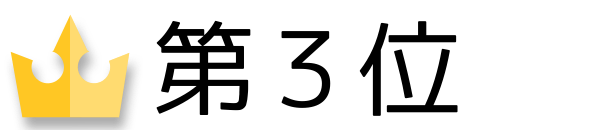
カードローンの基本概念
カードローンは、消費者金融会社が提供する個人向けの無担保小口融資サービスです。このサービスを利用することで、消費者は比較的迅速に資金を借り入れることができます。
- 無担保であるため、借入に際して資産を担保にする必要がありません。
- 審査は通常、迅速に行われ、申込みから融資までの時間が短いのが特徴です。
- 返済方法や返済期間は、借入先の金融機関によって異なります。
- 金利は固定金利と変動金利があり、金融機関によって異なります。
- カードローンの利用限度額は、審査によって決定され、個人の信用度によって変動します。
カードローンの申込みプロセス
カードローンの申込みは、通常、オンラインまたは金融機関の窓口で行われます。
- 申込みには、身分証明書や収入証明書などの書類が必要になることが多いです。
- 金融機関はこれらの情報をもとに審査を行い、借入れの可否を判断します。
- 審査には、信用情報機関に登録されている個人の信用情報が利用されることがあります。
返済に関する注意点
カードローンの返済にはいくつかの注意点があります。
- 返済は、金融機関ごとに設定された方法で行われます。一般的には口座振替やATMでの返済が可能です。
- 返済遅延には遅延損害金が発生する場合があります。
- 返済額には元本と利息が含まれるため、総返済額は借入額よりも多くなることが一般的です。
利用時のリスクと注意事項
カードローンの利用にはリスクも伴います。
- 高金利での借入れは、返済負担を重くする可能性があります。
- 借入れの過剰な利用は、借金の返済が困難になるリスクを高めます。
- 借入れと返済の履歴は信用情報機関に記録され、将来の融資に影響を与える可能性があります。
まとめ
カードローンは便利な金融サービスですが、利用には注意が必要です。金利、返済条件、自身の返済能力をよく考慮した上で、慎重に利用することが重要です。また、利用する金融機関選びにも注意を払う必要があります。